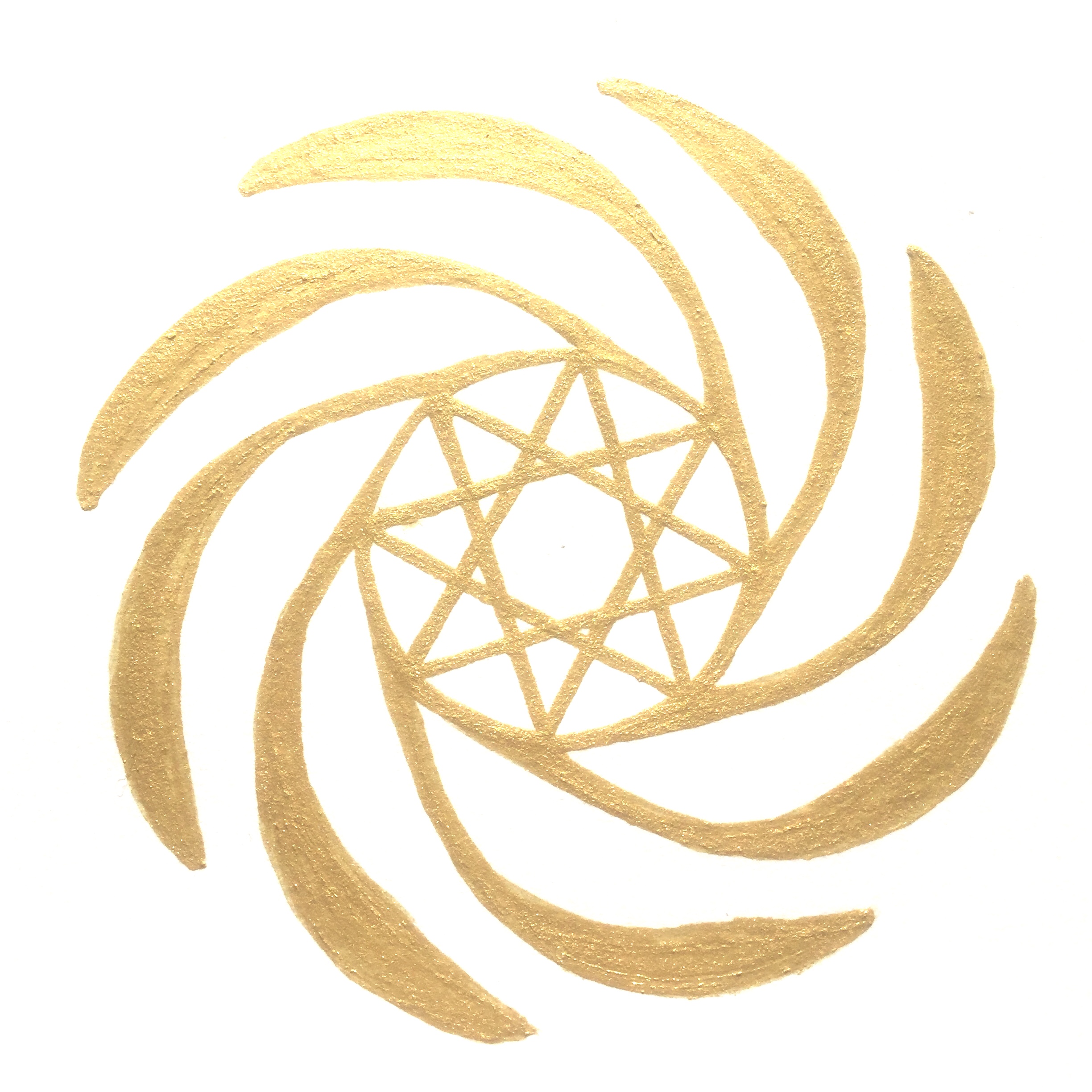20歳を超えたあたりから、徐々に“私も社会の一員である”という自覚が強くなっていったように思います。
・
社会の一員であるということは、自分の暮らしは社会を構成する他者のおかげで成り立っている、ということでもあります。
自分の身近な人や物について、それがどのように存続しているか少し考えるだけでも、想像しきれないほど膨大なモノが関わっていると分かります。
・
大学時代は一人暮らしで、家事や学業、アルバイト、サークル活動などさまざまなことに取り組みましたが、“自分のことは自分でやる”という経験をたくさん積んだおかげで、親元で親に頼りきりの生活をしていた頃には全く意識していなかった、“社会”というものをより身近に感じられるようになりました。
・
私は他者に支えられながら生きている。
そして、巡り巡って私も誰かを支えている……。
そう思うと、私は「もっと頑張りたい!」という気持ちが湧いてきます。
・
また、大学時代にはそれまでと違い、親や先生以外の大人と関わる機会も多くありました。
いつでも気にかけて面倒をみてくれる親でも、自分から尋ねなくても教え導いてくれる先生でもない、大人。
・
決してお手本にしたくないような大人にも会いましたが、幸運なことに、私の周りには親切で頼りがいのある大人が多かったです。
失敗を許し、寄り添いながら挑戦を促してくれたアルバイト先の先輩。
身心の不調により長期間通学できなかった私の学びをサポートしてくれた教授。
生きづらさの解消を手伝ってくれたカウンセラーや主治医。
つらいとき心の支えになるようなアドバイスをくれた人たち………
たくさんの大人たち、先駆者たちの支えがあったおかげで、私は荒波の中を渡ってくることができました。
・
先ほど、巡り巡って私も誰かを支えているといいましたが、実際のところは「私も誰か/社会を支えているんだ!」という明確な感覚を持つことはできていません。
家庭など少人数の社会ならまだ分かり易いですが、この広大な社会の一体どこに自分の力が作用しているのか、想像を膨らませることはできても実感することはなかなか難しいと思います。
・
そうして、「非力でちっぽけな私は、誰かのため/社会のために一体何ができるだろう?どうあるべきなのだろう?」と悩んだ末、2つの考えが浮かんできました。
(少々長くなってしまったので、前編と後編に分けて投稿する予定です。どうぞお付き合いください。)
・
1つ目は
【若者は、頑張る姿を示すことで、導き手である先駆者たちに多少の恩返しをすることができるのではないだろうか】ということです。
・
大学時代、3年弱ほど学内の保健室でカウンセリングを受けていました。
そこでカウンセラーさんから「星見さんは、これまで診てきた中で一番カウンセリングのしがいがある学生ですよ。あなたと話していると、カウンセラー冥利に尽きると感じることが多いです」といわれたのを今でも覚えています。
私が毎回しっかり彼女の話を聞いて覚えたものを、試行錯誤して自分の生活に応用して、きちんと経過を報告しに行くということを続けた結果、彼女はひたむきに頑張る私を見て「この仕事に就いてよかった」と思えたそうです。
・
自分のためにやっていたことですし、むしろ迷惑をかけてしまっていると思っていたので驚きましたが、私もとても嬉しかったです。
そのことを思い出して、1つ目の考えに至りました。
・
自分が築き上げてきたものが誰かの役に立った、自分が育ててきたものが実を結んだ……そう思えたら、頑張ってきてよかった!もっと頑張ろう!と、気持ちが押し上げられますよね。
若者のひたむきに頑張る姿は、それを支え、育てる先駆者たちにとって、生きる希望や更なる活躍のモチベーションになるのではないかと考えています。
・
若者が大人たちに支えられて奮起し、その姿を見て大人たちが元気づけられ、双方が成長できる土壌がつくられていく………
そうして社会全体で良い方向に進んでいけたらいいなぁと思います。
・
そのためにも、これまで支えてくださった方々への恩義を忘れず、まずは自分から、頑張る姿を積極的に示していきたいと思っています。
この成長記もその活動の内のひとつです。
・
星見の成長記を読んでくださっている皆さま。
いつも応援してくださっている方々。
皆さまに少しでも恩返しができるよう、これからも励んでまいります。
・
・
さて、次回、後編では「私は誰かのため/社会のために何ができるのか?」という疑問への2つ目の考え、【道を拓く】についてお話しします。
次回もどうぞよろしくお願いします。
・
星見